動きの改善で健康や競技力の向上を目指すセンター誕生
2024年5月17日掲出
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 中山 孝 教授 斎藤 寛樹 助教

この4月から蒲田キャンパスに設立された「ヒューマンムーブメントセンター」。子どもから高齢者、さらにアスリートまで、あらゆる人の"動き"の改善を目指すセンターとして始動しています。今回は、このセンターの概要や具体的な取り組みについて、中山先生と斎藤先生にお聞きしました。
■今回設立された「ヒューマンムーブメントセンター」とは、どのようなセンターですか?

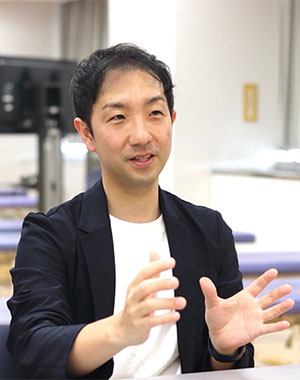
もう少しわかりやすく説明すると、ムーブメントとは対象者が達成したいパフォーマンスや身体活動があったとき、その基礎部分にあたるものです。例えば、野球でバットをスイングするということは、簡単に言うと、バットを持って、投手がボールを投げるタイミングに合わせて身体をねじり、バットを振るという動作ですよね。それを分解すると、単純な身体のねじり動作や腕を上げる、腕を回旋するという基本動作に分けられます。つまり、私たちはスポーツのバッティング動作にフォーカスするのではなく、その動作の基礎となる単純な動きにフォーカスすることで、対象者が様々な動きをできるようにサポートするのです。それが理学療法の専門性ですから、そこを活かしたセンターとして活動していきます。
■4月から始動した同センターですが、具体的に今、進んでいることや、今後、取り組んでいこうとお考えのことを教えてください。
中山:斎藤先生がお話しされたように、身体活動のベースにあるファンダメンタルムーブメント(基礎的運動)は、人である限り共通項です。人は生まれて、首が座り、腰が反り、座り、立ち、歩き、走れるようになり…という一連の基本的なムーブメントを、誰しもが経験します。そのムーブメントを正しく捉えるために、機械を使って、客観的なデータを取ります。そして「あなたの動きはこうですよ」と提示する。例えば、関節の動きであれば、3次元動作解析で捉えることができます。また、関節を動かしている筋は筋電図という装置で測定できます。そういったものを組み合わせると、この時間帯にこういう関節の角度になっていて、そこからどれくらいのパワーが出ていて、それによって目的とする動作ができているということを数値で証明できます。それを元に、動きを正常に近づけるための努力をしますし、なかなか正常に達しない人には、さらにその人に合ったトレーニングプログラムを作って提供したりもします。 このようなことを実現するには、何よりまずデータが必要です。また対象者にとって最適な活動のパターンを知るには、それらのデータを人工知能で解析し、それをフィードバックすることが大切です。そういう取り組みを始めています。


斎藤:具体的な話をすると、痛みを持った患者さんやアスリートなど、対象者の方々に本学へ来てもらい、まずはその方たちの動きを定量的に分析します。実はこの動きのデータを取ることが、今の医療現場やスポーツ現場ではマンパワーや機材の関係でなかなかできていないことなのです。そういう点でこのセンターの独自性とも言えますが、3次元カメラやセンサーを使い、まずは動きのデータを取って解析し、それに基づいて対象者にフィードバックし、実際に介入を手伝います。介入とは基本的には運動療法のことです。
例えば、スクワットをきれいにする場合、ここのストレッチをしましょうとか、ここの筋力トレーニングをしましょうというように具体的に提案します。また、最近では、電気刺激を使って筋力トレーニングの効果をさらに高めるといったこともしています。色々な手段がありますが、そもそも最適な手段を選択するには、きちんと測定・解析する必要があるため、それらを一連の流れで行います。


また、当センターは、大きく2つの部門に分けて進めています。ひとつは、ケガをした人を扱う「スポーツ障害部門」です。スポーツ障害と聞くと、アスリートのイメージがあるかもしれませんね。ですが、そもそも"スポーツ"の語源は、ラテン語の「deportare」で、気晴らしをするとか余暇を楽しむといった意味があるそうです。ですからスポーツは限られたアスリートだけのものではなく、子どもから高齢者まで誰もが対象になります。ケガをしているアスリートにも、腰が曲がって日常生活がうまくできない高齢者にも対応する部門になります。
もうひとつは「ハイパフォーマンス部門」です。こちらは、アスリートに特化していて、高く飛びたい、球を早く投げたいといったスポーツ選手に対して、さまざまな介入方法を開発する部門で、基礎研究の分野になります。これらの部門での取り組みは、私たちの研究対象でもありますから、その成果は学会などで発表し、分野を盛り上げていくことも大切な要素のひとつです。
また、当センターの存在や取り組みを、広報活動を通じて広めていくこともします。実際に高校を訪問し、私たちのアイデアや理学療法士の面白さを宣伝していく予定です。高校には部活をしているアスリートたちもたくさんいますから、彼らのデータを測定して、パフォーマンスを高める支援も行うつもりです。それにより理学療法は面白いということを感じてもらい、結果として、本学への入学希望につながればと考えています。

中山:補足としては、対象者に本学に来て頂いてデータを取ることに加えて、持ち運びできる機材もあるので、今後は実際にアスリートのいるグラウンドへ出向いて、計測することも考えています。このアスリートのいる現場で計測するということには、非常に意味があります。早速、計測を始めようと、今、計画しているところです。
斎藤:そうですね。本学はスペースの関係上、実際のスポーツ動作などのダイナミックな動きをする場所がありません。それらをきちんと測定しないといけませんから、そういう場合は選手のいるフィールドまで出向いて測定することも重要だと思います。 また、今、病院とも提携を結び始めていて。ケガをしている人と当センターをつなぐ役割を病院にしてもらうことが必要です。また、学校の部活動の先生方と連携することも考えています。さらに踏み込で言うと、最終目標として、蒲田キャンパスへ世界中から有名アスリートに来てもらい、動きを計測・解析するということも考えています。最終的には、そこまでもっていきたいですね。
中山:蒲田キャンパスは羽田空港(東京国際空港)から近いですし、国内であれば東京駅や品川駅へもすぐにアクセスでき、利便性が非常に高いです。これから実績を作り、世界でもトップクラスのムーブメントセンターを目指していきたいところです。
斎藤:実際に今、国内のプロアスリートやサッカーチームと連携し、データの測定や解析が始まっていますからね。

中山:例えば、現在、プロテニスプレーヤーの方の動きを測定しています。この選手がボールを打つときのインパクト部分のデータを取って分析し、それをフィードバックすることも少しずつ始めている段階です。この選手の場合、足裏に痛みがあって本来のパフォーマンスが発揮できないという課題を抱えています。そこで私たちは、なぜ痛みがあるのかを色々なデータを解明することで見つけ出し、どういう理由で足に負担がかかり痛みにつながっているのかを対象者にフィードバックします。それがわからないまま、長期間、これまでのようなスイングや練習方法で活動していると、将来的に選手として長続きしませんし、痛みの再発や悪化の可能性も高まります。それをどう予防しながら整えていくかという教育的な指導もできるわけです。そんなふうに長期間にわたってアスリートがパフォーマンスをキープできるように、あるいは今ある痛みを軽減して、良いパフォーマンスに持っていけるようにすることも私たちの役目です。
斎藤:理学療法分野には、これまでの蓄積として正常な体の動きのデータがありますから、そこからどう外れているのかを計測し、正常に持っていくための方法を提案することができます。また、最近では測定したデータをより正確に解析するには、人工知能を用いることが重要な手法になるとも言われています。ですが、私たちはその分野の専門家ではありません。そこで八王子キャンパスの片柳研究所にできた「デジタルツインセンター」の先生方に加わってもらい、人工知能による解析のサポートをして頂いています。
中山:学部や分野を超えて、本学の強みを発揮する一つの手段になり得るという点も、当センターの存在意義だと思いますね。
■ヒューマンムーブメントセンターの取り組みに、学生はどのように関わるのでしょうか?
斎藤:基本的に学生の関わりは不可欠です。今、お話しした「デジタルツインセンター」での人工知能による解析も教員がオーガナイズしてはいますが、実際の解析は、学部生や大学院生にも手伝ってもらいます。ただ、今回のセンターの場合、プロのアスリートを対象とすることもあるので、慎重さが求められる重要事項については教員が行うようにしています。その重みづけはプロジェクトによって変わってきますが、学生が参加する機会は設けられています。中山:まだ設立して間もないセンターですから、在校生を始め、職員にも当センターの存在が認知され始めたばかりという状況です。ですから今後、学内においても、このセンターの存在や取り組みを視覚的にも口頭ででも、積極的に宣伝していく必要はありますね。
斎藤:将来的には、このセンターが広く知られるようになって、そこに関わりたいという希望を持って入学してくれる学生が増えてくれると一番良い形ですからね。
■今後の展望をお聞かせください。
中山:今の話の延長になりますが、入学した時に、先輩たちがこういうセンターで活動していて、計測したり教員と一緒になってイキイキと何かに取り組んだりしている姿を見せることは、とても重要だと思います。リハビリテーション学科の場合、3年生頃から卒業研究ゼミが始まるので、学生から学生へとセンターの取り組みが伝わっていくと理想的です。そういう形で、連綿とつないでいける息の長いセンターになると同時に、日本有数のムーブメントセンターとして名が通り、学生からも高校生からも自然と注目される存在になってほしいですね。本学科にはまだ大学院の課程がありませんが、いずれ設立されれば卒業後に大学へ戻り、当センターで計測したり研究で論文を書いたりすることにもつながるはずです。また、今はムーブメントを中心に据えて展開していますが、ムーブメントを支える要素はたくさんあります。体の健康だけでなくメンタル部分での健康も必要ですし、そのメンタルを支えるには十分な栄養や睡眠が必要です。先ほど斎藤先生から「デジタルツインセンター」との協働の話がありましたが、分析のために人工知能を動かしてくれるエンジニアの力も必要ですし、睡眠の研究者や体の特定の部位や神経系の働き・機能を分析する人など、色々なエキスパートの力が必要になります。そういう方たちを複合的にこのセンターに集めて、将来的には多様な学際分野エキスパートの融合体となり、幅広いことにチャレンジできるチームにしたいというのが願いです。
斎藤:そうですね、最終的にはそういうトップレベルのセンターにしていきたいです。先ほど、世界のトップアスリートに当センターに来てもらえるようにしたいと言いましたが、チャレンジングなことではあっても、現実的に妥当な展望だと思っています。というのも、繰り返しになりますが蒲田は羽田空港から電車で約10分という抜群のロケーションです。また、日本特有の話として、今、ケガをしているアスリートが来日し、医療を受けるケースが徐々に多くなってきているとの話もあります。それというのも、日本は世界と比べて医療のサービスが良いからです。例えば、骨折やじん帯を損傷したかもしれないとき、画像で撮って、どうなっているかを見る、MRIやCTといった画像診断がありますよね。それが日本は優れています。また、日本は病院へ行くと、すぐに画像を撮ってくれますが、実は欧米でそういうことができるところは多くありません。ケガをした時にまず病院へ行き、レントゲンを撮ることになっても、その予約が1ヵ月先にしか取れなかったりします。それを待っている間にもうケガが治っているなんてケースも多々あって。私も定期的に整形外科のクリニックで働いていますが、先日も外国人の方を対応した際に、医師による的確な診断、理学療法のレベル高さや優れた医療機器には驚いたとの感想も伺いました。ですから、日本の優れた医療サービスを受けるために世界中から来日する人がこれからさらに多くなるのではと予測しています。
私たちとしては、この流れを活かして画像撮影だけでなく、それにプラスして運動機能を測定できるとなれば、パフォーマンスを高めたいアスリートや身体機能を改善してケガや病気を予防したい人がさらに多く利用してくれるようになるだろうと期待しています。その実現に向けて、取り組んでいくつもりです。
中山:我々の強みは海外からの患者さんのデータをもらって評価をし、メニューを作って、きちんと運動までできるようにすることです。その人のための最適な運動メニューを作り、もし長く日本に滞在できるのであれば、滞在期間中のプログラムを作ってフォローし、良くなったかどうかの評価もします。そして自国に戻れば、自分でリハビリやトレーニングをしてもらうという連携もできます。そういう治療からリハビリまで、日本で完結できるということが世界中に広まれば、うれしいです。
斎藤:アスリートの場合、ケガが治ることだけでなく、パフォーマンスの部分で競技に復帰できるかどうかも大事ですから、そこまでを一連でできるようにしたいのです。病院でも、例えば高血圧や高コレステロールなど、内科的な疾患ではきちんと血液検査をして、それをもとに薬を処方するなどしますよね。ところがリハビリの分野でなかなか治らないのは、そういうデータをきちんと測定できておらず、最適な介入ができていない可能性が高いのです。もちろんデータを測定して、こちらから取り組んでほしい運動メニューを提供しても、実際に運動するのは患者さん自身ですから、全く運動をしてくれないということもあります。ただ、こちらができることとして、まずはきちんと測定が行われていないという点を解決し、治らない人を治るようにしていこうと考えています。ただし、本学は医療機関ではありませんから、治療ではなく、あくまでも治療をサポートするという姿勢です。
中山:本学は教育機関ですからね。医療に携わるとした場合は、あくまでも計測したデータを学術的に検証し、病院へ評価結果を提供する形で関わることになるだろうと思います。
斎藤:ただ、ケガをしている人ではなく、アスリートがパフォーマンスを上げたいというケースであれば、病院とは関係なく、直接メニューを提案して、取り組んでもらうことが可能です。また、例えば腰痛を病院で診てもらって良くなったという人が、腰痛の再発を予防したいということであれば、当センターが直接介入することができます。
中山: そうですね。あとは、現状、当センターの広さや設備が世界中のアスリートを受け入れるには十分ではないので、これから実績を作って、実際にアスリートが走れるようなトラックをつくるなど、このセンターを拡張できればと思い描いています 。
■最後に受験生・高校生へのメッセージをお願いします。
中山:今、アメリカのメジャーリーグで大活躍している大谷翔平選手ですが、彼の素晴らしい業績や成果を支えているのは、彼の身体であり、モチベーションの高さであり、精神的な強さです。それらを融合することで、あのパフォーマンスが発揮されています。皆さんの中には、そのようなアスリートを支えたいから理学療法士になろうと思っている人もいるでしょう。これからの時代にアスリートをサポートするには、やはり信頼される科学的なデータに基づいた理学療法の展開が不可欠です。将来、そういう分野で活躍したいと考える高校生は、ぜひ本学の門をたたき、今回、紹介したセンターを介して色々な勉強をし、自分の夢を実現してください。もちろん、お子さんからお年寄りまで、さまざまな人の健康を増進させたいという願いを持って理学療法士を志す方も多いと思います。健康を通して人々を支えたいという方も、ぜひ本学で幅広い学習をしながら、将来の夢を叶えてください。
斎藤:アスリートにはパフォーマンスを高めたいとかケガを治したいという思いがありますし、一般の方にはケガを治したい、あるいは仕事で存分に力を発揮して業績を残したいという思いがあります。そのためには身体機能、つまり健康を整えることが最重要事項だと思います。その中でも、身体活動の基礎となる"動き"をサポートする専門職が、私たち理学療法士です。この仕事は、本当に動きが良くなって旅行に行けるようになったとか、動きが良くなってケガなくスポーツを楽しめるようになったとか、ずっと座って仕事ができるようになったといった対象者の声を直接聞くことができ、感謝してもらえる、とても素敵な職業です。理学療法士を志す学生が、そういうことを体験できるように全力で教育したいと思いますので、ヒューマンムーブメントセンターや本学部に興味を持ってもらえるとうれしいです。
また、本学部はグローバル人材の育成にも力を入れています。今回のセンターを通して、海外からアスリートに来てもらうこともありますし、海外から一流の教員を招いて講義してもらうことも増えるでしょう。常に教育では最先端・世界標準レベルを目指しているので、そういった教育が受けられるというところも魅力です。
中山:その通りです。国際レベルで活躍できる人を目指す方は、ぜひ本学部で学んでほしいですね。そもそも今回のセンター自体が国際化を目指していますから、それに準じた教育を提供することができます。


