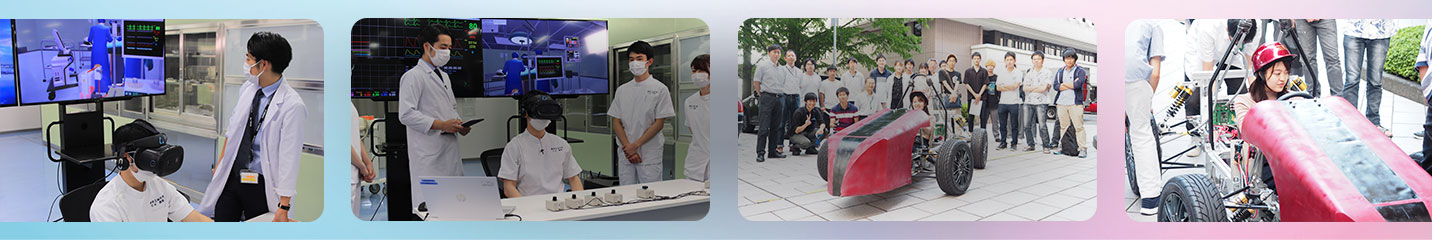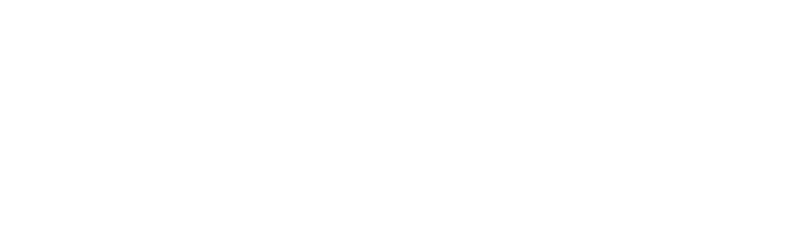戦略的教育プログラムについて
東京工科大学では、理工系総合大学の強みを生かし、実践的な学びを提供するために、時代のニーズや社会の要請に応じた「戦略的教育プログラム」を展開しています。各学部ごとに専門分野を生かした独自のプログラムを設け、最新技術や実社会での活用を見据えた学びを通じて、学生一人ひとりが未来で活躍できる力を身につけることをめざしています。
これらのプログラムは、「実学教育の推進」「教育力の強化」「社会の要請に基づく教育」の3つの柱に基づき、高い専門性と実践力を養う内容となっています。
>>2021年度~2024年度の戦略的教育プログラムはこちら
>>2017年度~2020年度までの戦略的教育プログラムはこちら
学部別 戦略的教育プログラム
工学部
AI/DXを活用した創造型モノづくりエンジニアの実践教育プログラム
~学内自律移動ロボット・無線給電システムの開発~

代表教員
高橋秀智
専門分野:CAD/CAMシステム、ヴァーチャルリアリティ、マンマシン・インタフェース
モノづくりが変わってきている。自律型ロボット、スマートフォンに代表されるように、モノの目的や機能の多元化・統合化が進み、DX/AIによりできなかったことが可能になった。このような時代に際し、エンジニアやエンジニア教育の発想の変化が求められている。従来のスペシャリストから、様々な技術分野の統合設計が可能なπ型人材、さらには、デザイン・ソフトウェア・コンテンツまで担えるフルスタックエンジニアの要求が高まっている。一方、DX/AI技術の高度化により、設計・解析・シミュレーション・製造などのツールの進歩は著しく、統合設計やフルスタックエンジニアリングを低学年で経験し学びを深める環境が整ってきている。
本プログラムでは、通常カリキュラムにおける、設計シミュレーションツールやAI生成ツールを活用した演習の導入とともに、優秀な学生や上昇志向の高い学生に対し、ロボットカーやEdgeデバイス(回路・アンテナ)を題材にし、低学年より統合設計・開発、フルスタックエンジニアリングを行う実践工学プロジェクト演習を設定し、人材育成を行う。
世界と地域,世代をつなぐ!AI/DX活用型
グローカルSTEAM教育推進プログラム
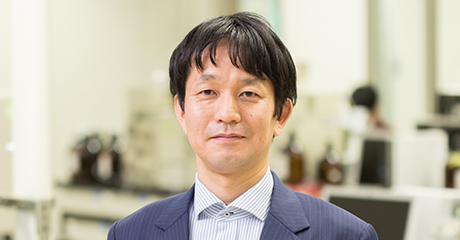
代表教員
原賢二
専門分野:触媒化学、表面科学、物理化学、有機合成化学
社会が激しく変化し、多様な課題が生じている今日、文系・理系の枠にとらわれず、各教科等の学びを基盤としつつ、様々な情報を活用しながらそれを統合し、課題の発見・解決や社会的な価値の創造に結び付ける資質・能力の育成が求められている。文部科学省では、STEM(Science, Technology, Engineering, Mathematics)に加え、芸術、文化、生活、経済、法律、政治、倫理等を含めた広い範囲をArtと定義し、各教科等での学習を実社会での問題発見・解決に生かすための教科等横断的なSTEAM学習の実施を推奨しているが、小中高校のみで独自に実施することが困難な状況にある。この状況の中、高等教育機関である大学がSTEAM学習の一端を担うことが求められている。
そこで、本プログラムでは、本学の学生自らがAI・DX技術を活用して、①海外や地域との実際の連携を通して社会課題を発掘し、その課題解決や社会的価値の創造を目指す機会を創成し、②その成果を踏まえて、小中高校で必要とするSTEAM教育用デジタルコンテンツを制作し、③国内外の小中高校に提供する。
本プログラムの実施により、次世代を担う国内外の小中高校での教育に本学が貢献できると期待される。また、正規のカリキュラムでは容易に修得することが困難である、国際的な素養、社会・地域の課題解決能力、AI・DX技術の応用手法を修得した学生を育てる機会を創出できると期待される。
コンピュータサイエンス学部
実社会データ利活用コンピューティング
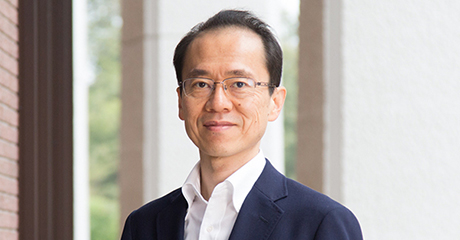
代表教員
細野繁
専門分野:サービス工学、サービスコンピューティング、設計工学・システム、標準化
実社会では、ビッグデータやIoT(モノのインターネット)などの技術進展により、多種多様なデータが日々生成されている。本教育プログラムでは、これらのデータを効果的に収集、解析、視覚化し、その成果を実践的に応用するスキルを育成し、ビジネスの最適化、政策立案、医療診断、環境保護など多様な分野での革新を見通せるようにする。
実施教員の専門性を活かして、専門分野毎に単年~数年間のプロジェクトをメニュー化し、プロジェクトベースの課外活動を行っていく。実施教員の課題の探索のリードの下、学生は現状分析~課題の特定を行う。課題解決に関わるデータの収集と前処理のスキルとして、データベース管理、データクリーニング、データ統合などを行う。データ解析のスキルとして統計的手法や機械学習、人工知能(AI)を用いたデータ解析手法を実習し、データから有用な情報を抽出する力を養う。データの視覚化については、発表機会を通じて解析結果をわかりやすく他者に伝えるスキルを身につける。また、企業・団体との協働を通じて倫理的問題やプライバシー保護についても理解を深める。データの不正利用や個人情報の漏洩等のリスクへの対策を試行しながら修得する。
以上のプログラムを通じて、学生は実社会の具体的な問題をデータ駆動型で解決する能力を養い、ビジネス、公共政策、医療、環境など様々な分野でデータを活用した意思決定できる人材に成長できる。
メディア学部
メディア・クリエイティブアクション・プログラム
~学生主体活動への支援を提供する学部内インキュベーションプログラム~

代表教員
羽田久一
専門分野:モノのインターネット、メディアアート、バーチャルリアリティ、エンタテインメントコンピューティング
本プログラムは、IT技術とコンテンツ制作のスキルを融合させたプロジェクト型学習を基盤に、「学内インキュベーション」をコンセプトとして、学生が主体的に企画・制作・運営を行う活動を支援するものである。この支援には、メンタリングや資金面でのサポートが含まれ、特に資金面などの課題で実現が難しかったアイデアの実行を後押しすることを目的とする。学生は、自ら課題を発見し、解決策を設計し、成果を具体的な形で発表するまでの一連のプロセスを通じて、将来的なキャリア形成や社会的価値の創出を目指す。具体的なプロジェクト例として、デジタルコンテンツ作品の展示会の開催、地域企業とのブランディング企画の推進、ファブリケーションラボの運営、メタバースを活用した教育プログラムの提供などが挙げられる。さらに、プログラムの2年次以降には、学生から提案されたアイデアを審査し、支援対象となる活動を選抜する仕組みを構築することを目指す。
本プログラムは、あらかじめ設定された演習項目を単にこなすのではなく、学生自身が主体的に取り組む活動を支援する仕組みを提供することを目的とする。また、特定の専門分野に限定するのではなく、メディア学部で得られる多様な学びを統合的に活用することを目指し、実践を通じてその能力を養う場である。さらに、プロジェクト終了時には、実施内容に対する評価の場を設け、活動全体に対するフィードバックを提供すると同時に、成果物の完成度を高める意識を学生に植え付けることも目指したい。
応用生物学部
AI・デジタル技術を活用できる人材の育成教育プログラム
~デジタル資格の支援、AIでつくるプレゼンテーション、AIでつくる化粧品~


代表教員
藤沢章雄、矢野和義
専門分野(藤沢章雄):反応化学、有機化学
専門分野(矢野和義):生物工学、分子生物学
現代社会ではAIやデジタルの技術が急速に発展し,すでに多様な領域での応用が広がっている。一方,これまで応用生物学部ではバイオテクノロジーを基盤とした4つのコースでの教育・研究を推進してきたが,特にAI・デジタルを意識した教育を積極的に推進することは行ってこなかった。このため,AI・デジタルの知識や技術が学生に身につくことはほとんどなく,結果的に将来の問題解決のため積極的に活用しようというマインドも醸成されてこなかった。そこで,本プログラムでは,学生にAI・デジタルに関する基礎的な知識を体系的に学んでもらい,その成果としてこの分野での関連資格の取得を促すことを目的とする。またAI技術を学生実験の発表資料の作成に活用し,学部長賞発表会で披露してもらうこと,さらにAIを活用した新しい化粧品の開発を目指すことも目的とする。具体的には,以下の3つのプログラムを実行する。
①AI/DX関連資格の取得支援(統計検定(2,3級,データサイエンス基礎),バイオインフォマティクス技術者認定試験,LC分析士,LC/MS分析士)
②AIに関する学修とプレゼンテーションへの応用
③AIを活用した新規化粧品の開発
医療保健学部
ストーリーマップをAI言語モデルへ応用した
医療技術の反復実習プログラム

代表教員
苗村潔
専門分野:医用機械工学、コンピュータ外科学、看護理工学
2050年超高齢社会では医療従事者不足は深刻となり、より高度な能力を備えた医療従事者を、効率的に養成することが必要である。
医療従事者間の語りによる情報伝達、患者からの訴えに臨機応変に対応する現状から、インタビュー音声情報の質的分析によるストーリーマップ作成と医療技術を俯瞰的に把握する能力、ストーリーマップを用いて多職種共創により課題の抽出、改善策を提案する能力を養成する。
在学中に実施される学生間での患者想定演習では実際との乖離が大きく不十分となっているため、ストーリーマップをAI言語モデルに応用した教材を開発する。また、空き時間に医療技術を反復練習できるよう、デジタルツイン環境に指導ポイント動画、ストーリーマップを搭載する。
医療×テクノロジー×デザインの融合による医療ICT開発ラボの構築:
次世代ヘルスケア人材育成プログラム

代表教員
友利幸之介
専門分野:意思決定支援のためのアプリ開発、リハビリテーションにおける目標設定、作業に焦点を当てた実践
本教育プログラムでは、医療保健学部、コンピュータ・サイエンス学部、デザイン学部の3学部が連携し、医療ICT関連のプロダクツを教員と学生とが実際に開発するためのラボを構築する。このラボにおける開発研究を通して、学生は所属学部における専門的かつ実践的な知識と技術を習得しつつ、今後求められる必要な学際的なコミュニケーションスキルの獲得も期待できる。
アジアの医療機器管理を変える!
~医療機器のDXリーダー育成プログラム~

代表教員
島峰徹也
専門分野:臨床工学、医用生体計測工学、医療治療機器学
医療デジタルトランスフォーメーション(DX)についての実践的な専門力を有した国際人の育成を目標として、上記プログラムを提案する。プログラムを通じて、国際的な視野とコミュニケーション能力を持った、時代に柔軟に対応できる国際人の育成に貢献する。また、これから大きな発展の見込めるアジア地域の医療現場の実態を観察することで、臨床工学技士の強みである医療機器や医療機器管理教育の医療DXについてのギャップを把握し、より実践的な提案ができる人材育成と、本校が将来の医療DX構想に一役を担えるよう、アジアの医療機関との関係構築を確立し、MOU締結、共同研究、学生誘致に活用する。
デザイン学部
戦略的ブリュワーズ:
AIと協働するグラフィック/ブランディングデザイン

代表教員
葛原俊秀
専門分野:ブランディング、サービスデザイン、広告
本教育プログラムの目的は、生成AI(以下、AI)との協働によるグラフィックデザインの可能性の拡張と検証にある。デザイン学部の視覚デザインコースと情報デザインコースが連携して行うこととし、視覚デザインコースの教員による株式会社大鵬との共同研究(クラフトビール「白蒲田」の開発研究)をベースとして、クラフトビールのパッケージを題材とした展開を行う。学生にとってこれまで培ったデザインの知見をAIと協働することにより、本質的なデザインの価値を再認識すると共に、デザインという文脈におけるAI活用の知見と可能性を体得する機会となることが期待される。
デジタルツインを活用した教育プログラム
~シミュレーション・アーカイブ・エクスペリエンスで探求する新しい空間デザイン~

代表教員
小山祐輔
専門分野:空間デザイン、VR(仮想現実)
デジタルツイン技術やAIを活用し、現実空間と仮想空間の融合を図ることで、次世代の教育プログラムを構築します。このプログラムを通じて、学生は最新技術を活用した実践的なスキルを習得し、防災や観光、地域活性化といった社会課題に取り組む力を養います。
世界的にデジタルツインの研究は急速に進んでおり、スマートシティ※1やスマートインフラ※2、アートアンドテック※3、モビリティー※4など、多様な分野でその応用が展開されています。このような情勢において、本プログラムは都市空間や地域資源道路(山間部道路や観光ルート道路)のデジタル化を通じて、新たな地域支援モデルを提案し、地域社会との協働による実践的な学びを実現します。さらに学生がプロジェクトを通じてデザイン分野での問題解決能力を実践的に学ぶだけでなく、デジタルツイン技術の普及や社会実装を促進することで、持続可能な未来への貢献を目指します。
※1 スマートシティ:都市全体をシミュレーションし、交通や防災、エネルギー効率化を実現するデジタルツイン技術。
※2 スマートインフラ:デジタルツインで橋梁やトンネルの状態を管理し、維持管理の効率化や劣化診断を可能にする技術。
※3 アートアンドテック:デジタルツイン技術を活用し、仮想空間での新たな芸術表現や観客体験を創出する分野。
※4 モビリティー:自動車や公共交通のデジタルツインを使い、運行最適化や自動運転の検証を行う技術分野。
教養学環
AIで進化する教養教育
─問題発見・解決の地平を拓く─

代表教員
加用一者
専門分野:天文学、宇宙物理学
AIの教育現場での活用には極めて大きな期待が寄せられている。一方で、教育は人の在り方に強く介入するものであるから、その実施については慎重にならなければならない。これまでの実績のある方法とは異なる新奇な方法を導入するときは、特にそうである。果敢にかつ慎重に進めるために、本プログラムにおいては、教養学環の幅広い科目分野の多くに対して、小さく挑戦することにした。まずは、AI (主にいわゆる生成系AIとよばれるもの) との親和性の高いとされる3つの分野 (外国語、文章表現、プログラミング技法) に関わる授業の一部にAI利用を主体としたクラスを設置し、その教育効果を慎重に検証する。その結果、その他の分野にも発展させることができることがわかったならば、果敢に拡大させる。
以下に3つの分野ごとに具体的な目的を記述する。
(1) 英語
1.AIを活用した英作文添削の教育的効果を調査する。
2.AIを用いた英作文の添削プロセスを通し、学生の英作文能力向上を分析する。
3.AI添削の成果に対する日本人学生とネイティブスピーカーの認識の違いを比較することで、教育現場でのAI活用の可能性を検討する。
(2) アカデミックスキルズ
生成系AIを真に利用するということは、何かを生成するということに他ならない。生成AI時代の大学リテラシー教育、すなわち、情報を批判的に評価し、効果的に活用しながら自ら文章を生成・修正する能力を涵養する教育プログラムの開発を行う。
現在の生成系AIが生成する文章には、特徴的な文体のパターンや語彙の不自然な偏りがある。そのため、どれだけAIが発達しても、学生自身の文章能力を磨かなければ、AIの生成したものを越える文章を作成することはできない。AIを使いこなして文章を作成しつつ、自分の文章力も深め、AIの生成したものを越える文章を書けるようになることを目指す。
(3) リベラルアーツ特論 (天文データ解析)
天文学などの科学技術の諸分野におけるビッグデータを、AIやデータサイエンスの手法を使い解析・議論・問題解決を行うことで、社会における様々な問題に対処する実践的な学びを身につけることができる教育プログラムを提供する。